はじめに
皆さまお疲れさまです。
今回、ビジネス書で効率的な勉強法について学ぶことにしました。
今回紹介するのは、安川康介さんの『科学的根拠に基づく最高の勉強法』です。著者の安川さんは臨床医として働きながら、勉強法についてのYouTubeチャンネルも運営しており、実践的なアドバイスを発信しています。
私自身、今年は学びたいことがたくさんあります。
- がん専門薬剤師試験(再来年受験予定)
- 英語の習得
- 栄養・薬学の知識向上
- ブログ運営スキルの向上
- NFT出品の学習
また、親として子供の教育にも役立つかもしれないと考え、この本を手に取ってみました。
本書の中で特に印象に残ったエッセンスを、わかりやすくまとめていきたいと思います。
1. アクティブリコール(能動的に思い出すこと)
本書で繰り返し強調されているのが「アクティブリコール」の重要性です。
勉強の際に、単に情報をインプットするだけではなく、以下の方法で能動的に思い出すことが有効だと述べられています。
- 定期的に思い出す
- テストを受ける
- 誰かに話す
「思い出す」というプロセスが記憶を定着させる鍵となるため、例えば次のような方法が推奨されています。
- 新しい範囲を勉強したら、少なくとも1~3回内容を思い出せるまでアクティブリコールする
- 1日~1週間後に再度アクティブリコールを試す
- 何度か繰り返すことで、長期記憶へと移行する
2. 分散学習(時間をあけて勉強する)
一度に長時間勉強するよりも、時間をあけて複数回学習する方が効果的であるとされています。
例えば、2時間連続で勉強するより、1時間×2回に分けて行う方が記憶に残りやすいそうです。
間隔の取り方には諸説ありますが、本書では「とにかく時間をあけて復習することが理にかなっている」と強調されています。
3. 内発的モチベーションを高めるために必要な3つの要素
勉強を継続するためには、内発的なモチベーションが重要です。本書では、以下の3つの要素を満たすことでモチベーションを高められると述べられています。
- 自律性:他人に強制されずに自分の行動を選択・決定できること
- 有能性:自分が何かを上手にできるという実感や、特定のタスクや挑戦を成功させる能力
- 関係性:他人とのつながりや帰属意識を持つこと
「朝学」をうまく活用することで、これらの要素を達成しやすくなると感じました。
4. スキマ時間の活用
勉強時間の確保が難しい場合でも、日常のスキマ時間を活用することで効率的に学習できます。
具体的なスキマ時間の活用例
- 通勤時間 → 音声学習や暗記カードを使う
- 休憩時間 → 簡単な復習
- トイレの時間 → アクティブリコール
短時間でも、繰り返し思い出すことが学習定着に役立つことを再認識しました。
5. 勉強に使えるツール:Anki
本書で紹介されていたツールの中で特に気になったのが「Anki」というアプリです。
Ankiとは?
- フラッシュカード型の暗記アプリ
- 分散学習のアルゴリズムを活用し、記憶定着を促進
- 医学生や語学学習者の間で特に人気
まだ使ったことがないので、今後試してみようと思います。
詳しい解説は以下のブログに記載されているので、参考にしてみてください。 Ankiについての詳細
6. 学習方法の実践プラン
本書の内容を踏まえ、今年は以下の方法で勉強を実践してみようと思います。
- インプットしたことを軽くまとめる
- 朝学ブログやnoteに投稿(文章化することで理解を深める)
- スタンドFMで「誰かに教える気持ちで」話す
- ②や③を定期的に見直す(時間をあけて復習)
- 行き詰まったら@校長くんAI に質問する(ポジティブな意見を得る)
ツールやコミュニティを活用しながら、皆さんと一緒に学んでいけたらと思います。
7. まとめ
『科学的根拠に基づく最高の勉強法』を読んで得た学びをまとめると、
- アクティブリコール(思い出すことで記憶定着)
- 分散学習(時間をあけて学習する)
- モチベーションを維持する3要素(自律性・有能性・関係性)
- スキマ時間の活用
- 記憶ツールの活用(Ankiなど)
などが、効率的な勉強を進める上での重要なポイントでした。
また、「勉強の効果は、勉強している本人には実感しにくい」そうなので、焦らず長期的な視点で取り組んでいこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
皆さんが実践している勉強法や、オススメの学習ツールがあれば、ぜひ教えてください!
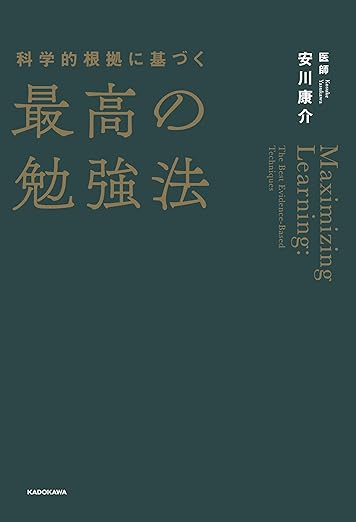


コメント