目次
はじめに
私は調剤薬局で1年間、病院で12年間、薬剤師として働いています。今回は、病院薬剤師の仕事内容を詳しく解説し、薬学大学生向けに専門的な視点も加えて紹介します。
診療薬局と病院薬剤師の違い
一般的に薬剤師というと、調剤薬局での仕事をイメージしやすいですが、病院薬剤師はその役割が大きく異なります。調剤薬局では、医師が発行した処方箋に基づいて調剤を行い、患者さんに薬を提供します。
一方、病院薬剤師は調剤だけでなく、注射薬の調製、服薬指導、医薬品情報管理、治験管理 など、多岐にわたる業務を担っています。また、患者さんの病状や検査値を考慮しながら薬物療法を最適化する役割も果たします。
病院薬剤師の主な業務
調剤業務
病院では、内服薬、外用薬(貼り薬、塗り薬など)、注射薬 などを取り扱います。医師が電子カルテで処方した薬剤について、以下の点をチェックしながら調剤を行います。
- お薬の指示内容が正確か
- 患者さんの腎機能・肝機能を考慮した適切な用量か
- 他の薬剤との相互作用はないか
特に病院薬剤師は、抗生物質や抗がん剤など、投与量の設定が重要な薬剤の調整に関与します。腎機能障害のある患者には腎排泄型薬剤の投与量を減らす必要があるため、クレアチニンクリアランス値を確認することが求められます。
その後、調剤した薬は各病棟に払い出され、患者さんに使用されます。
注射薬の混注業務
病院薬剤師の重要な仕事のひとつに、注射薬の混注業務 があります。特に抗がん剤の調製は、高い専門性と正確性が求められます。
- 医師の指示が的確かを再確認
- 必要な量を慎重に採取し混注
- 無菌環境で調製し、適切な形で提供
混注時には無菌操作が必須であり、クリーンベンチや安全キャビネットを使用します。誤った混注を行うと、投与時に重大な副作用が発生する可能性があるため、徹底した管理が必要です。
服薬指導
病院薬剤師は、病棟のベッドサイドで、患者さんに薬の使い方を説明 します。
- 患者さんの理解度に応じた説明を行う
- 副作用の確認と適切な対応
- 服薬アドヒアランスを向上させるための工夫
特に抗がん剤や免疫抑制剤の服薬指導では、副作用マネジメントが重要です。患者さんが適切に服薬できるよう、定期的なモニタリングとサポートを行います。
専門性を高める業務
医薬品情報管理
病院薬剤師は、最新の医薬品情報を収集し、医療スタッフに提供する役割も担います。
- 新薬の効果・副作用の評価
- 投与設計のガイドライン策定
- 医療スタッフ向け勉強会の開催
医薬品情報室では、医師や看護師からの問い合わせに対応し、エビデンスに基づいた適切な情報提供を行います。
治験業務
新薬の開発には臨床試験(治験)が必要であり、病院薬剤師はその管理を担当します。
- 治験薬の管理と投与スケジュールの調整
- 被験者の安全管理
- データ収集と評価
治験コーディネーター(CRC)と連携し、治験が適切に実施されるようサポートします。
チーム医療への参加
病院薬剤師は、多職種連携の中で活躍する機会も多いです。
- 感染症チーム(AST): 適切な抗菌薬治療を支援
- 緩和ケアチーム: 終末期医療の薬物療法を支援
- 栄養サポートチーム(NST): 栄養療法の調整
医師や看護師、管理栄養士と連携し、患者さんにとって最適な治療を提供します。
おわりに
病院薬剤師の仕事は多岐にわたり、専門性が求められる場面が多いです。単なる調剤業務にとどまらず、患者さんの治療効果を最大化するための役割を担っています。
薬学大学生にとって、病院薬剤師は挑戦しがいのある職種のひとつです。より専門的なスキルを身につけ、医療チームの一員として活躍できるよう、今後も学び続けていきましょう。
これからも、薬剤師の仕事について詳しく解説していきますので、ぜひ引き続きご覧ください!

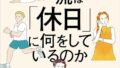

コメント