皆さまお疲れ様です!
さて、今日は半藤一利著
●「日本のいちばん長い日」
●「昭和史 1926-1945」
を紹介します。
戦死者を悼みつつ、今も世界で戦争が続く中で、感じたこと、考えたことを書いていきたいと思います。
「日本のいちばん長い日」で描かれていた切ない人物
約80年前の1945年8月14日夜から8月15日朝7時ころまで、最後の反乱が起こり、収束しました。
80年前・・・遠い昔のようでいて、実はごく最近のお話であることに、改めて驚かされます。
畑中少佐(映画で松坂桃李さんが演じていました)のクーデター、そして失敗、自害が主軸としてあります。
ここについては、「国(天皇)を思う気持ち」「軍人のエゴ」が入り交じり、善悪では語れない、大変複雑な感情となりました。
本文中で記載があった通り、畑中少佐はある意味「純粋な軍人」であり、若者の熱さと純真さも加わり、非常に哀しさを誘う人物です。
私より若いですし、
戦争が無かったら、きっと青春を謳歌していたのだろうか、などと思いつつ、
毎年終戦の日には彼を思い出すことになると思います。
「昭和史」で最後に語られる教訓
「昭和史」は授業形式でわかりやすい語り口で読みやすい+綿密なデータで非常に読み応えがありました。
その中で、最後に教訓として書かれている部分が最も心に残りました。
抜粋してみます。
①国民的熱狂を作ってはいけない
②最大の危機において日本人は抽象的な概念論を非常に好み、具体的な理性的な方法論をまったく検討しようとしない
③日本型のタコツボ社会における小集団主義の弊害(エリートが小集団を作り、他からの情報を認めないなど)
④国際社会の中の日本の位置づけを客観的に把握していなかった、常に主観的思考による独善に陥っていた
⑤何かことが起こったときに、対症療法的な、すぐに成果を求める短兵急な発想をし、その場その場でごまかし的な方策で処理した結果、時間的空間的な広い意味での大局観が持てない
どうでしょうか?
私はこれを読んだとき、「今も変わっていないかもしれない・・・」と思ってしまいました。
このことは繰り返し思い出し、まずは自分から、行動を見直していかなければならないと思いました。
何をすべきでしょうか
今もウクライナや中東の戦争は続いており、混沌としています。
一刻も早い収束を望みつつ、昭和史などを読むと、「戦争を終えることがいかに難しいか」についても学ぶことができました。
太平洋戦争のように戦力差が圧倒的であってもこれだけ難しいのですから、多国が介入して戦力が拮抗している+(日本には無かった)歴史的な領土問題が絡むと、なおさら難しいのだと思いました。
一個人でできることはとても少ないですが、
世界を見る、世界の中での日本を見る
これにいっそう意識を向ける必要があると思いました。
様々なテクノロジーで世界につながっているように見えて、無料で得られる情報には限界があります。
日米の金利差は未だ拡大しており、円安がさらに進む可能性もあり、海外の情報を得るコストがさらに高くなる懸念もあります。
それでも、コストをかけて情報をとりにいき、語学を学び、もっと世界を見なければいけない、と思い、
「朝礼だけの学校」でよく言われている「大人が学ぶ姿勢を子供に見せることが最大の教育」を実践したいと、改めて思いました。
月並みな感想になってしまいましたが・・・
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という諺の通り、
日本史、世界史については大人になってからより一層学ばなければいけないかもしれません。
半藤一利先生の本は他にも多くあり、色々読んでみたいと思いました。
最後に
昭和天皇の聡明さ、凄さが最も印象に残り、昭和史の最後は感動して少し泣きそうになりました。
読まれていない方は、これから秋の夜長の読書におすすめです。
戦争体験者がどんどんいなくなる中で、風化させない努力は大切だと思いました。
皆様は戦争、終戦についてどのように考えますか?
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
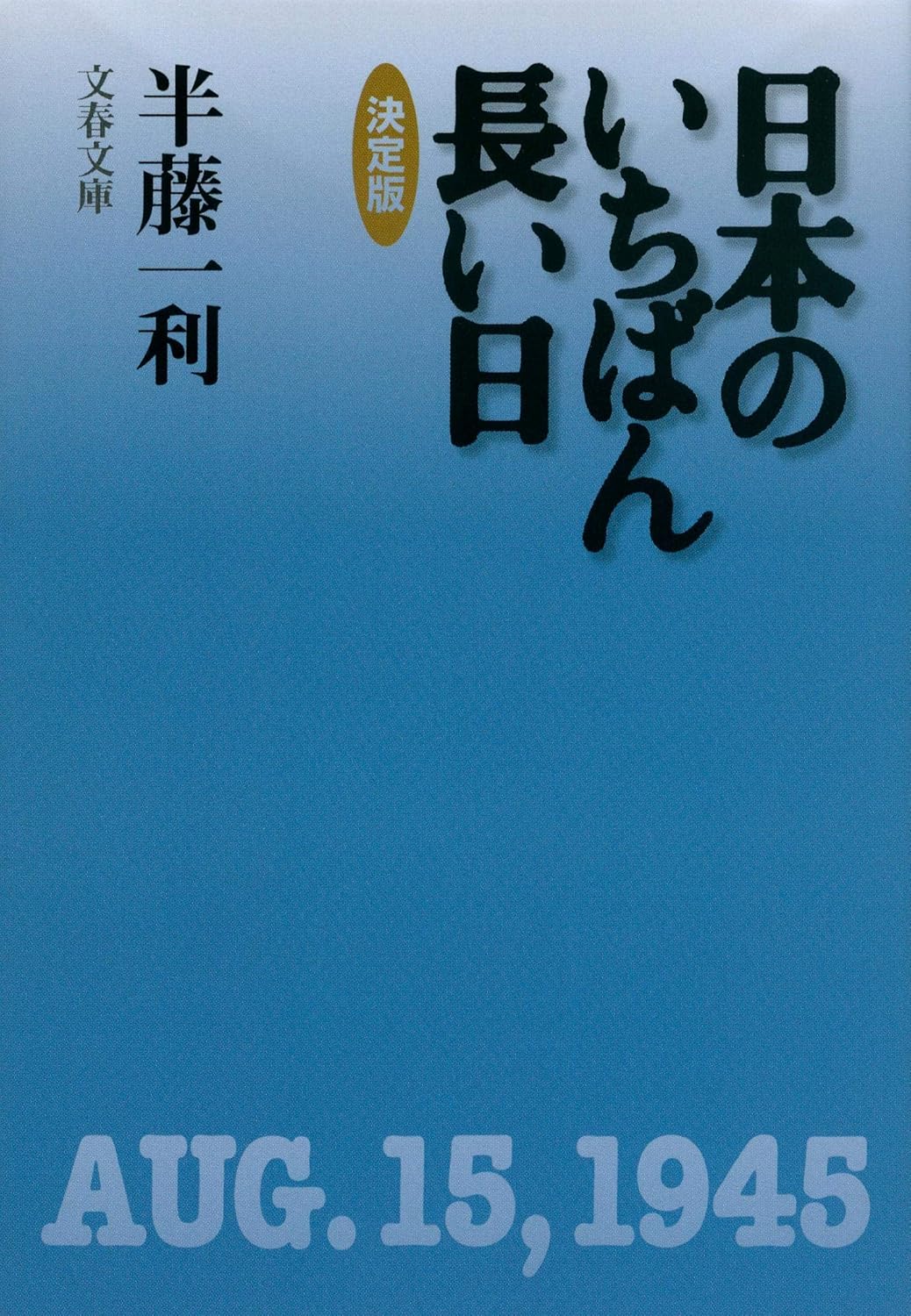


コメント